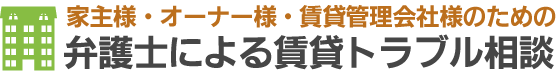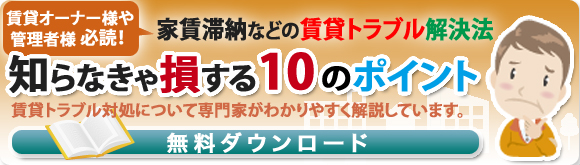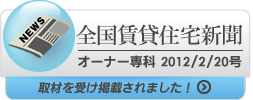契約期間終了前に契約を終わらせるための3条件
![]()
このケースは、入居者側が期間満了前に契約を「終わらせたい」と思っているという点で、前のケースとは逆のパターンになります。
一定の期間を定めた賃貸借契約において、契約期間中に入居者の側から契約を終了させる方法としては、次の3つがあります。
① 契約の解除
② 合意解除(合意解約)
③ 特約による解約権の行使
このうち①の契約解除は、貸主が契約で定められた通りに建物を使わせていない(債務不履行)といった事情があり、信頼関係が破壊された場合に限り解除が可能になります。逆にいえば、このような明確な事情がなければ、契約の解除はできません。
次に、②の合意解除(合意解約)は、①のような事情がなくても、貸主と借主の双方が賃貸借契約を終了させることに合意した場合には、契約が終了するというものです。
もっとも、合意解除は、当事者の双方の合意が必要なので、いくら借主側が契約の終了を求めても、貸主の側がこれに応じなければ、この方法で契約の終了はできません。
このように、貸主側に債務不履行がなく、合意解除にも応じてもらえないという場合、借主側が講じてくる可能性のある手段とはどんなものなのでしょうか?
賃貸借契約書を確認してみましょう。契約書の特約で「契約期間内に賃借人がこの契約を解約するときは、3カ月前に予告するか、予告後3カ月分の賃料を支払わなければならない」と定められていれば、借主がこの特約に従って契約を終了させる手段に出ることも考えられます。
「定期借家契約」期間途中の場合
中途解約などの賃貸トラブルの解決法をまとめた無料小冊子
「賃貸トラブル解決法 知らなきゃ損する10のポイント」をご用意いたしました。
詳しくはこちらからご確認できます。
![]()
2年間の契約期間でマンションの1室を貸したのですが、借主が結婚して新居で暮らすことになったため、解約を申し出てきました。現在の部屋は、契約満了まで1年以上期間が残っているのですが、残りの期間の賃料は請求できるでしょうか?
立退き料はどう決まる?
ところで、立退き料はどのように決まるのでしょうか?
立退き料は、移転経費(引っ越し費用、移転通知費用)や、借家権の価格、営業補償、地縁的なつながりを失う精神的苦痛などを考慮して決定されます。ただ、具体的な金額は、定型的な計算式が存在しない以上、一概には言えません。
貸す側・借りる側双方の年齢や経歴、職業、資産、経済状態、健康状態、家族関係、法人である場合には設立時期や従業員数、経営状態など、さらに土地や建物に対する事情(建物の経過年数や老朽度、近隣状況、使用目的など)を考慮に入れて総合的に判断せざるを得ません。
一般論としていえば、貸主側の明け渡しの必要性が高ければ高いほど立退き料は低額になりますし、借主が建物を営業用として利用している場合は、営業補償が含まれるので、提供される額も高額になるでしょう。
本事例の場合も、建物がそれほど老朽化していなければ、借主としては住み続けたいはずです。しかも今まで違反がないという以上、明け渡しを求める理由としては弱いため、相当額の立退き料の支払いを条件に、明け渡しが認められる可能性があるでしょう。
なお、金額の算定にあたっては、前述のように、老朽化の度合いや周辺の事情に照らした経済的効用の程度が、考慮されることはいうまでもありません。
立退き料の支払いは義務ではない
最後に⑤の「立退き料」について、見ていきましょう。
立退き料は、建物の明け渡しの条件として支払う場合(支払いは明け渡しよりも先)と、明け渡しと引き換えに(同時に)支払う場合がありますが、必ず支払わなければならないものであるとは限りません。
この点、東京高裁平成3年7月16日判決は、建物の基本構造部を含めて老朽化が顕著な事案において、貸主の建物使用の必要性がなくとも立退き料の支払いを考慮して正当事由を認めています。
東京地裁平成3年11月26日判決は、老朽化がひどく地盤崩壊などの危険性がある建物について、これを取り壊して貸主の生活の基盤となるような新しいビルを建てる必要性があるとして、立退き料がなくとも、明け渡しの正当性を認めました。
また、最近の裁判では、建物の高度再利用を目的とする場合には、高額の立退き料の支払いを条件に、「明け渡し」の正当性を広く認める方向にあります。
たとえば、あまり傷んでいない建物であっても、貸主から事業拡張のための建て替えという名目で明け渡しを求められる場合がありますが、こうした場合は高額の立退き料の支払いさえあれば、明け渡しが妥当と判断されることが多いようです。
その明け渡しには正当事由があるか?
![]()
結論から言えば、貸主が一定の条件を踏んでおり、また建物を建て替えざるを得ないような事情がある場合は、借主に立退きを要求強要できます。その際に、立退き料を払わなければならないケースも考えられます。
借地借家法28条、26条では、契約が更新されない要件が定められています。
1. 事前の通知
貸主は借主に対して「契約期間満了後は契約を更新しない」という内容の通知を、契約終了の1年前から6カ月前までに行う必要があります。この通知は、証拠を残すために、配達証明付内容証明郵便で行うべきでしょう。
2. 使用に対する異議の通知
このような通知が送られて契約期間が終了してもなお、入居者主が部屋(建物)の使用を継続するという場合は、貸主としては、速やかに使用に対する異議を通知すべきでしょう(そうしないと、借地借家法26条2項により、これまでと同じ条件で、期限が決められていない賃貸借契約が更新されたとみなされることになりかねないからです)。
ここで留意したいのは、異議の通知をしても、明け渡しの「正当な理由」が認められなければ、貸主は更新を拒絶できないということです。
「正当な理由」については、
① 貸主・借主が建物を必要とする事情
② 貸し借りのそれまでの経過
③ 建物の利用状況
④ 建物の今の状況
⑤ 立退き料
を考慮して判断されます。
このうち、①は、居住の必要性や営業の必要性です。
このケースでは、入居者がこのアパートに住む必要性が認められますが、貸主側は新しいマンションに建て替えたいだけですので、アパートを使用する必要性はあまり認められません。
もっとも、新しく建て替えたマンションからの賃料収入が生計の唯一の手段である場合は、貸主にもこの建物を使用する必要性があるといえます。
次に、②は、貸し借りをした事情や、家賃の相当性、契約期間中に賃料不払いや信頼関係を破壊する行為があったかどうかなどです。
このケースでは、借主は家賃をきちんと支払っていますし、他には契約違反はないようです。ただし、ここで留意したいのは、借主が建て替えのことをいつ知ったか、です。
「貸し借りをした事情」として、借主が、将来的にアパートが取り壊されることを知ったうえで借りていた場合には、「明け渡し」を拒めない可能性があります(東京地裁/昭和61年2月28日判決)。
③は、借主が契約違反などをせず、有効に部屋(建物)を使っていたかどうか、また、実際にはあまり使用していなかったという事実はないか、が考慮されます。③の判断については、①や②と重なる部分があるでしょう。
④は、建て替えの必要性の有無、また、社会的・経済的効用が十分あるか否かという点から判断されます。
借主に落ち度はないが…
![]()
古くなったアパートを撤去してマンションを建築する予定で、現在の契約が終了したら更新をしないつもりです。借主はいままできちんと家賃を払っており、契約違反もありません。立退き料を払う義務はありますか?
造作と有益費。違いはどこに?
有益費は、建物を構成している一部分で、壊さなければ分離できないもの。造作は壊さなくても分離できるものです。
しかし、この区別はあいまいで、貸主の同意の有無という基準もあります。有益費の場合は貸主の同意を必要としませんが、造作の場合は必要です。
さらに、買い取りを求める価格は、有益費の場合は支出した実費か価値の増加額のうち賃貸人がどちらかを選択できるのに対し、造作の場合は時価という違いもあります。
支払いが済むまでは物件を明け渡してもらえない?
では、造作買取請求権が認められる場合、借主から造作の時価が支払われるまでは建物を明け渡さないと主張されても仕方ないのでしょうか?答えはNOです。
借主側からすれば、造作によって建物の利用価値が増加している以上、その費用を支払ってもらえるまでは建物を明け渡したくはないと考えるかもしれません。
しかし、判例(最高裁判所昭和29年1月14日判決)は、反対に、造作の時価が支払われないことを理由に明け渡しを拒否することはできないという結論を採っています。これは、造作と建物の明け渡しはあくまでも別であるという考えに基づいています。
特約の内容に注意!
ここで注意したいのは、造作と認められさえすれば、自動的に賃貸人に対して買取請求ができるわけではないということ。造作は、貸主の同意を得て設置されなければならないという前提があるのです。
また、特約の内容にも注意が必要です。賃貸借契約をかわす際に、契約終了時に造作買取請求権を放棄する旨の特約(賃貸人の買取義務を免除する特約)が交わされた場合には、この特約は有効となります。したがって、貸主は買い取り請求を拒むことができるのです。
さらに、契約がどのように解消されたかという点も重要です。賃貸借契約が、債務不履行(賃料不払いなど)や、賃借人の背信行為を理由として解除された場合には、賃借人には造作買取請求権が認められません(最高裁判所/昭和31年4月6日判決)
追加で備え付けた設備費は請求される可能性がある
![]()
借地借家法33条1項は、建物の賃借人(入居者)が、賃貸人(大家)の同意を得て建物に追加で備え付けた畳や建具などを、賃貸人に時価(支出した費用ではありません)で買い取るよう請求できる権利を定めています。これを「造作買取請求権」といいます。
「造作」とは、判例(最高裁判所/昭和29年3月11日判決)によれば、「建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊の目的に使用するため特に付加した設備は含まない」とされています。
過去にも、調理台やレンジ、食器棚、空調設備など飲食店としての使用目的に沿って、建物に便益を与えているものだとして、造作と認められた判例があります(新潟地裁/昭和62年5月26日判決)。また、別の裁判例では物干場、台所用釣戸棚、電灯設備、水道施設、電灯引込線などが造作として認められています。
しかし、造作かどうかという判断は、難しいところがあります。例えば、利便性が良くなっても、家具など独立性が強いもので、取り外しても物件自体の価値が減少しないものは造作とは認められません。
また、戸棚でも借主がその建物を特殊な目的に使用するために設置した場合は造作とは認められません。