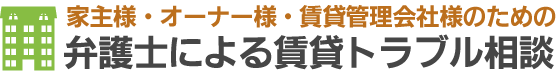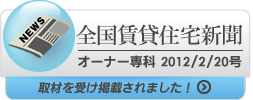クロス・カーペットは新品で返してもらえるか
![]()
4年間住んだ入居者が退去することになりました。契約には「借主は、故意過失を問わず、建物の毀損・滅失・汚損その他の損害につき損害賠償をしなければならない」という条項を設けてあります。クロスやカーペットなどをすべて新品にして明け渡すよう請求できるでしょうか?
返金は原状回復費用が確定してから
質問は、敷金はすぐに返還してもらえないのか、ということでした。
先ほど述べた通り、「通常使用による損耗」ではないキズや傷み、すなわち、借主が負わなければならない正当な費用は、敷金から差し引かれます。
ですから、原状回復費用が確定するまでは敷金を返せないという貸主の主張は、正当といえるでしょう。但し、いつまででも「原状回復費用が確定していない」という言い分が通らないのはもちろんです。物件を明け渡してもらったら、速やかに原状回復費用を確定させて、敷金を返還するようにしましょう。
敷金と原状回復義務
![]()
敷金とは、借主が家賃の支払いを怠った場合の滞納賃料や、物件を傷つけた場合の損害賠償金を担保するためのものです。
敷金は、契約終了後、物件を明け渡す際に借主に返還されます。ですから、「支払う」というより、貸主に「預ける」という認識が正しいと思われます。
ところで借主は、賃貸借契約を終了する際に、物件をもとの状態に戻して返還する義務があります。これを「原状回復義務」といいます(民法616条・598条)。
ここでは原状回復義務という言葉を、もう一度確認しておきましょう。「原状回復」というと、借主が部屋や建物を新品の状態にして、返すということではありません。
これは、入居後に新たな設備を付け加えた場合、それを取り外して返還することであり、原則として、新品同様にして戻す義務はないのです。
新築の物件をどんなに注意深く大切に使用したとても、長く使用していれば、ある程度の傷や汚れが発生します。こうした劣化を法律的には「通常使用による損耗」と表現し、その回復費用は貸主が負担するものとしています。
よって、常識的な使い方で発生した「損耗」に関しての回復費用は借主に請求できません。
問題は、借主がわざと、あるいは誤って物件にキズや汚れなどをつけてしまった場合で、
こうした「通常使用による損耗」ではないものの原状回復費用は請求できます。
さて、敷金は原状回復にかかる費用もまかなうものですから、どれだけの敷金が返ってくるかは、借主が負担すべき原状回復費用の金額に応じて決まることになります。したがって、敷金の返還と原状回復はセットで問題となるのです。
なお、敷金の返還額(貸主の立場から見た場合は原状回復費用)は貸主・借主の話し合いでの解決が望ましいのですが、意見が食い違う場合は、最終的に裁判所に原状回復費用請求(借主の立場から見た場合は敷金返還)訴訟を起こして、解決を図ることになります。
契約終了と同時に借主から返金要求が…
![]()
2年間住んだアパートの契約が終了したので、借主が契約時に預けた敷金を返すよう求めてきました。原状回復費用がまだ確定していないので、今は返せないと返答してありますが、やはり、すぐに敷金を返さなければならないものなのでしょうか。
はじめに
不動産トラブルで非常に多くの相談がある「敷金」の問題をとりあげます。
借主には物件を原状回復させて返還する義務があります。そのために必要な費用を敷金から差し引くことが多いのですが、差し引く金額を巡ってトラブルが起きがちです。
もし原状回復費用について、借主との間で対立が発生した場合は、どのように解決すればいいのでしょうか?
契約はどのように終了する?
最後に定期借家契約の終了について、補足しておきましょう。
法律では、決められた期間で契約を終了させる条件が定められています。期間1年以上の契約では、契約が終わる1年前から6カ月前までの間に、貸主が借主に対し、期間満了時に賃貸借契約が終了することを通知しなければなりません(借地借家法38条4項)。
では、この期間内に通知が行われなかった場合はどうなるのでしょうか。
通知が契約期間中であれば、契約終了は通知から6カ月後です(借地借家法38条4項ただし書き)。これが契約期間終了後になると、そこから6カ月後に終了するという意見と、契約終了には先の三つの条件が必要という意見があり、見解が分かれています。
なお、貸主、借主が再び賃貸借契約を続けたいという場合は、定期借家契約には契約更新がないので、新たに契約をとりかわす必要があります。
家賃滞納などの賃貸トラブルの解決法をまとめた無料小冊子
「賃貸トラブル解決法 知らなきゃ損する10のポイント」をご用意いたしました。
詳しくはこちらからご確認できます。
市価より高い家賃について減額の請求は可能か
家賃を支払わなければならなのであれば、借主としては負担をできるだけ抑えたいはず。そこで、家賃が相場よりも高い場合には、賃料減額を求めてくる場合があります。
この点、通常の借家契約では、家賃が相場よりも高すぎる場合、借主は減額請求をすることができます(借地借家法32条)。しかし定期借家契約では、「賃料改訂特約」の有無が問題になります。「賃料改訂特約」、つまり「賃料は○年ごとに○%ずつ増額する」という特約がある場合は、これが優先されるため、賃料の減額請求は認められない傾向にあります(借地借家法38条7項)。
本事例においても、このような「賃料改訂特約」があれば、家賃の減額を求めることはできません。そうなると、やはり契約期間満了までは賃料を支払う義務が生じます。
定期借家契約とは
![]()
「定期借家契約」は、契約時に定められた期間で契約が終了し、更新がない契約です。
定期借家契約が成立するために必要な条件は、次の通りです。
① 貸主が借主に対し、あらかじめ更新がない契約であり契約期間の終了により賃貸借が終了することを書面を通じて説明すること
② 契約書を作成すること
③ 一定の契約期間を定めること
ここで問題となっているのは、以上の条件のもとに定期借家契約がかわされたうえで、中途解約ができるかどうかです。
賃貸借契約を終了させる手段としては、相手方に契約違反があった場合の契約解除や、当事者双方が契約終了を合意する合意解除がありますが、本事例では、お互い契約違反も解除に関する合意もありません。また、契約書にも中途解約の定めはないようです。
借地借家法38条5項では、定期借家契約でも一定の場合には中途解約ができると定めています。ただし、その場合は、次の三つの条件をすべて満たしていなければいけません。
① 居住用の建物賃貸借契約であること(*)
② 床面積(建物の一部分が賃借物件であるときは当該一部分)が200平方メートル未満であること
③ 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の拠点として使用すること が困難になったこと
上記の条件を満たしている場合に限って、借主は解約の申し入れをすることができます(契約終了は、この申し入れから1カ月後)。
本事例では、中途解約に関する特別の決まりもなく、事業用にビルの1室を借りているので①居住用ともいえないため、中途解約は不可能という結論になります。つまり、借主は定められた契約終了期間まで家賃を支払う必要があります。
(*)
「居住用」の建物といえるかどうかは、契約が、借主が生活の拠点として使用する内容になっているか否かにかかってきます。
「定期借家契約」期間途中の場合
![]()
現在、仕事用にビルの1室を貸していますが、借主が仕事場を別の場所に移したいと言ってきました。契約は「定期借家契約」であり、まだ契約期間の途中ですが、中途解約しなければならないのでしょうか。契約書には、中途解約について何も定めてはいません。
特約がなければ期間満了まで家賃を請求できる?
本事例のような場合、新居に引っ越しても、現在の住居の家賃を支払わなければならない
のでしょうか?
原則から言えば、2年間の契約で賃貸借契約をかわした以上、その期間は賃料を支払うことで合意したわけですから、貸主の側に債務不履行がない以上、2年間は家賃を支払い続けなければなりません。
そうすると、新居と今の住居の家賃を二重に支払い続けることになるので、さすがに気の毒です。そこで、不動産賃貸業界における一般的な慣行としては、中途解約の特約がなくとも、2、3カ月程度の常識的な期間を定めて中途解約を認めているようです。
つまり、契約を終了させたい2、3カ月前に予告して、この期間が経過した後に明け渡すか、先に2、3か月分の賃料を支払い、即契約を終了させるか、を選ぶわけです。
ちなみに、借主が契約期間終了を機に更新をとりやめる場合には、貸主の場合と同様、契約終了の1年前から6カ月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ、それまでと同じ条件で期間の定めのない契約が更新されてしまいます(借地借家法26条1項)。ただし、この場合の通知は、貸主が更新拒絶する場合とは異なり、正当な理由は必要ありません。
もっとも、この更新拒絶の通知が必要な時期も、特約で「期間満了の3カ月前まで」などと定められていることが多いでしょうから、実際はその取り決めに従って契約を終了させることになります。
中途解約などの賃貸トラブルの解決法をまとめた無料小冊子
「賃貸トラブル解決法 知らなきゃ損する10のポイント」をご用意いたしました。
詳しくはこちらからご確認できます。