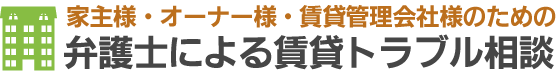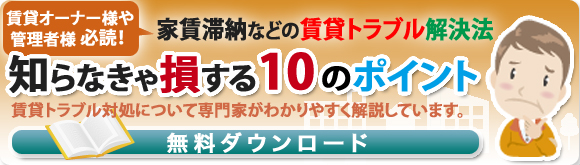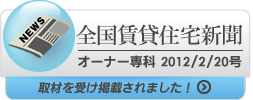まずは借主に更新拒否の通知を
![]()
では、営業中の店舗の賃貸契約を終了し、そこで自ら店舗を営業したいという場合です。
貸主は、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、借主に対し、更新を拒否するか、条件を変更しなければ更新しないという通知を「配達証明付きの内容証明郵便」で送っておきます。
さらに、期間満了をもって契約を終了させるためには、正当事由があると認められなければいけません(借地借家法28条)。
質問の事案では、営業目的で店舗の明け渡しを求めていますが、貸主が営業上の必要性を理由に契約を終了させることに正当事由が認められるかどうかが問題となるでしょう。
この点については、貸主の状況に応じてケース別に検討することが必要です。
物件を明け渡し要求が通る条件とは?
![]()
駅前にビルを所有しています。1階で自分の店を営業し、2階から上を人に貸していますが、自分の店が繁盛しているので、2階の契約を期間満了とともに終了させて自分の店舗として使いたいと考えています。契約を終了して、明け渡してもらうことは可能でしょうか。
「建物を必要とする事情」が判断に大きくかかわる
裁判所は、まず建物を使用する必要性に関して、貸主の事情と借主の事情を比較します。そのうえで、他の基準をあわせて考慮し、正当事由があるかどうか、つまり借主が部屋を明け渡すのはやむを得ないかどうかを判断するのです。
ちなみに貸主側の事情としては、その建物に住む、あるいはその建物で営業する必要性に加え、建物を解体・新築する必要性も含まれます。
POINT:立退料の提供も重要視される傾向に
⑤の「立退料などの提供」については、貸主が借主に立退料の提供を申し出たか否か、申し出た場合はその立退料の金額、また、貸主が代替家屋の提供を申し出たか否かなどの事情が考慮されます。
注意が必要なのは、この基準は他の事情により正当事由の条件がある程度満たされている場合に、参考までに検討される項目だということです。
したがって、いくら高額の立退料を提供したとしても、それだけで正当事由が認められることはありません。
POINT:営業用の建物は正当事由が認められやすい
最近では、住宅事情の緩和という事情を背景に、立退料の提供が正当事由の有無を判断するうえで重視されるようになってきました。
裁判所は、正当事由の条件が完全には満たされない場合でも、貸主が立退料を積極的に提供すれば「正当事由あり」と判断する傾向にあります。
特に営業用の建物の賃貸借においては、居住用の建物と比べると、立退料の提供の仕方次第で「正当事由あり」とみなされる余地は大きいと思われます(東京高裁/平成2年5月14日判決)。
もちろんこれは程度問題であり、借主が建物を必要とする事情が、貸主のそれを明らかに上回る場合には、どれだけ高額の立退料を提供しても、正当事由が認められないことは明らかです。
5つの基準で決められる正当事由
![]()
普通借家契約では、契約期間が終わっても、貸主に「やむを得ない理由」がなければ、契約はそのまま更新されます。ここでいう「やむを得ない理由」を、法律では正当事由(借地借家法28条)といいます。
立ち退きの正当事由は、
① 建物の貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情
② 賃貸借に関するそれまでの経過
③ 建物の利用状況
④ 建物の現在の状況
⑤ 立退料などの提供
など5つの基準を考慮して判断されます(借地借家法28条)。
法律ではこのようにさまざまな基準が挙げられていますが、正当事由の判断で重視されるのは、主に①の「建物を必要とする事情」、次に⑤の「立退料などの提供」も近年重視されています。
ここに注意、更新契約
一方、契約書などで、「更新料を支払わなければならない」などと書かれている場合には注意が必要です。この場合でも法定更新によって契約自体は更新するのですが、更新料を請求できるかどうか、が問題となるのです。
この点は、法定更新の場合にも更新料を支払う必要があるとするもの(東京地裁/昭和61年10月15日判決)と、法定更新の場合には更新料を支払う必要はないとするもの(東京地裁/平成2年7月30日判決)があり、判断が分かれています。
基本的には、契約書の書かれ方によって判断が異なってきます。たとえば、「賃貸借契約は合意により更新することができる。この場合には借主は、更新料として、新賃料の1カ月分を貸主に支払わなければならない」と書かれていたとします。
この場合、法定更新については一切書かれていませんから、素直に読むと、更新料を支払う場合は、「合意により更新する場合」だと解釈できます。したがって、法定更新によって契約が更新された場合には更新料を支払う必要がない、と判断されやすいでしょう。
しかし、反対に、「賃貸借契約が更新されたときは、合意更新であると法定更新であるとを問わず、借主は、更新料として、新賃料の1カ月分を貸主に支払わなければならない」と書かれている場合には、「法定更新」の場合も更新料を支払わなければならないよう書かれている場合、更新料を請求できる可能性があります。
さて、質問ですが、賃貸借契約に更新料の支払いに関する合意があれば、貸主は更新料を請求できます。では、借主が更新料を支払わなかった場合、更新料の不払いを理由に契約を解除できるのでしょうか。
一概には言えませんが、質問では更新料が家賃の1カ月分に過ぎず、更新料の不払いのみでは信頼関係が破壊されたといえない可能性が高いため、賃貸借契約の解除はできないと考えます。
もっとも、他に家賃不払いなど信頼関係の破壊をうかがわせる事情がある場合には、更新料の不払いが信頼関係破壊の理由の一つとみなされ、解除が認められる方向に作用することはもちろんです。
更新料などの賃貸トラブルの解決法をまとめた無料小冊子
「賃貸トラブル解決法 知らなきゃ損する10のポイント」をご用意いたしました。
詳しくはこちらからご確認できます。
合意更新と法定更新
![]()
賃貸借契約の更新には、貸主・借主間の合意によって更新される「合意更新」と、合意がなくても法律の規定によって自動的に更新される「法定更新」があります。
以下、この2つを分けて説明していきましょう。
当事者の合意で決まる……「合意更新」
合意更新の場合、更新料の支払いは、原則として当事者の合意により決まります。
賃貸借契約書の中に契約更新時には更新料を支払うことがはっきりと規定されていれば、「更新料が著しく高額で借主の利益を害するものでない」(借地借家法30条参照)限り、借主は合意に従って、決められた更新料を支払わなければなりません。
しかし、借主が契約時に更新料について説明を受けた覚えがなく、更新料の支払いの合意がない場合には、貸主は更新料の支払いを強要できません。
契約は自動更新される……「法定更新」
「借地借家法」では、次のように定められています。すなわち、貸主が借主に対して、契約期間満了の1年前から6カ月前までの間に、正当な理由のある更新拒絶の通知をするか、条件を変更しなければ更新しないという通知をしない限り、契約は前と同じ条件で自動的に更新されると規定されているのです。
これを「法定更新」といいます。
もし、更新料支払いについて合意がない場合、更新料を支払わなくても契約が自動的に更新されますから、借主は更新料を支払う必要はありません。判例も、借地に関する事案ではありますが、「更新料の支払い義務は慣習上認められるものではない」としています(最高裁/昭和51年10月1日)。
更新料は強制できるのか
更新料などの賃貸トラブルの解決法をまとめた無料小冊子
「賃貸トラブル解決法 知らなきゃ損する10のポイント」をご用意いたしました。
詳しくはこちらからご確認できます。
![]()
まもなくアパートの契約期間が満了します。更新料を1カ月分払って契約を更新するように言ったところ、「更新料を支払わないと契約は更新されないのでしょうか」と聞かれました。
家賃の減額を請求する場合は?
借主が、家賃の値上げを拒否するケースとは別に、家賃の「減額」を求めてくることもあるでしょう。例えば、現在住んでいるマンションが、周辺の同様の物件と比べて明らかに家賃が高い場合に、値下げ要求してくるケースです。
この場合も、家賃が貸主と借主の合意によって決まるという原則は変わりません。借主側による一方的な値下げはできないので、貸主と協議をすることになります。
協議しても合意が得られない場合、法的手続きをとることになり、調停か訴訟により正式な家賃額を決めるという流れは、値上げ拒否の交渉と同じです。
やはり法的手続きで解決までに時間を要しますから、この間はそれまでと同額の家賃を請求するべきでしょう。
裁判で借主から要求された家賃額(従前の家賃より安い家賃額)が認められれば、貸主は、その差額に年1割の利息を付した金額を借主に返還しなければいけません。
もっとも、家賃の減額を求めて訴訟を起こす場合も、多くの時間とお金(弁護士費用、不動産鑑定士に支払う費用など)がかかりますから、借主側では、訴訟を起こした場合に採算がとれるか見極めてから行動に移すと思われます。
以上のように考えると、借主が家賃の減額を求める訴訟で採算がとれるのは、家賃がかなり高額な場合(主に営業店舗やオフィスの賃貸借契約)に限られると考えられます。
借主は対抗手段を講じてくる
POINT:「借主が契約解除を免れるためのノウハウ」を把握しよう
契約が解除されれば、借主は生活の拠点を失います。そのような事態を未然に防ぐためにも、解除を免れる対策を講じてくることが予想されます。
方法としては、次の2つが考えられます。
①口頭の提供(民法493条)
借主は、「口頭の提供」を行えば、契約の解除を免れます。
「口頭の提供」とは、家賃を支払う準備をしたうえで、それを受け取ってくれるよう貸主に告げ、支払う意思を明確にすることです。ですから、借主が実際に家賃を貸主まで持参し、家賃を支払う意思を伝えれば、「口頭の提供」を行ったことになります。
②供託をする
借主が口頭の提供を行えば契約の解除はできませんが、家賃が徴収できないというわけではありません。
借主が家賃の支払義務を果たすため、「供託」という手続きをとることが考えられます。
供託とは、家賃を法務局に預けることにより、家賃を払ったのと同じ効果を得る手続きのことです。
手続きは支払場所を管轄する法務局で行われるので、通常は、貸主の住所地を管轄する法務局に家賃が供託されることになります。
なお、供託は口頭の提供をしたうえで行わなければなりません。口頭の提供がなければ、供託をしても家賃を支払ったことにはならないのです(最高裁/昭和32年6月5日判決ただし貸主の家賃を受け取らない意思が明確なときには、口頭の提供をすることなく直ちに供託をすることが可能)。
※ 供託の手続きを知っておこう
供託では「供託書」という書類を作成します。
この供託書には、家賃の値上げを要求されたことを含め、貸主が家賃の受け取りを拒絶し、目下係争中であることまで記載します。貸主の家賃を受け取らない意思を明らかにするためです。
また、供託は、数カ月分の家賃をまとめて預けることも可能です。貸主は口頭の提供が行われずに放置されていた家賃がまとめて供託される場合、放置期間が3カ月以上になると、家賃の不払いを理由として賃貸借契約を解除できます。
質問では「借主はこのまま支払う必要はないか」ということですが、借主が一切何も行わなければ、家賃不払いを理由に契約を解除できます。
家賃支払いがなければ契約を解除できる可能性あり
![]()
家賃の受け取り方には、以下の2種類あります。
①借主が貸主方に家賃を持参する持参方式(振り込みを含む)
②貸主が借主方に家賃を受け取りに出向く取立方式
通常の賃貸借契約では、①の方法がとられていることが多いので、ここでは持参方式を前提に説明します。
貸主に直接支払う方法であれば、借主は受け取りの強要ができません。よって、借主に支払う意思があるのに支払えない事態に陥ります。このような場合、貸主は受け取りを拒否した分を家賃の不払いとみなし、賃貸借契約を解除できます。
ここで注意したいのは、原則として貸主が一方的に賃貸借契約を解除できない、ということ。さらに、もし一方的に賃貸借契約の解除をしたいのであれば、借主に「義務違反行為」が認められなければなりません。
借主側には様々な義務があります。家賃の支払いも、そのひとつです。たとえ貸主が家賃を受け取らなかった時でも、家賃の不払いが発生すればそれを理由に契約を解除できる可能性があるのです。