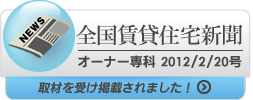無断で大幅なリフォームをされた!
賃貸物件の所有権は、貸主が有していますから、借主が無断で増改築をすることは認められないのが原則です。借主が賃貸物件の増改築をすることが認められるのは、貸主に承諾を得た場合のみになります。
焦点となるのは、では、借主が無断で増改築をした際に、契約解除が認められるかどうかという点です。判例などを参考にすると、信頼関係が破壊される境界となるのは、「建物の構造そのものに手を加えるか」でしょう。
賃貸借契約書に、「借主は、貸主の承諾なく増改築、改装、模様替えをしてはならない」という文言が入っていても、建物の構造に影響を与えない限りは許されることがほとんどです。たとえば、借主所有の家具、カーテン、カーペットを変更しても、建物の構造には何ら影響がないので、この行為を許せない!という貸主はいないでしょう。 一方、壁紙、床、ドアなどの改装は、建物の構造に影響を与える範疇に入ってくる可能性があります。
しかし、最終的には、増改築のトラブルも他の多くのトラブルと同様、最終的には、「それによって貸主と借主の信頼関係が破壊されたか」が判断材料になります。
現実的には、壁紙を替えた程度では、信頼関係が破壊されたとまでは言えず、契約解除は難しい可能性が高いでしょう。
ただし、借主は貸主に対して、退去時に「現状回復義務」があるので、もし、壁紙を元に戻さず退去しているのであれば、張り替え費用を借主に対して請求するのは妥当といえます。
契約と異なる用途で使いはじめた!
入居者の勝手な行動としては、「使用目的に違反している」というものもあります。通常の賃貸契約は、予め使用目的を決めて締結しています。借主は、この使用目的を守って物件を使用しなければなりません。これは、法律用語では、「用法遵守義務」と呼ばれます。
具体的なトラブルとしては、使用目的が住居となっているのに、オフィスや教室として使いはじめたというケースなどが考えられます。また、オフィスビルの場合は、使用目的がオフィスとなっているのに勝手に店舗をオープンしたというケースなどが想定されます。
では、これらの使用目的違反に対して、ただちに賃貸借契約が解除できるのでしょうか。
用法遵守義務違反の過去の判例では、契約解除が有効になったことも、無効となった場合もあります。契約解除が有効となるのは、使用目的を違反することで、「建物全体が大きな不利益をこうむった時」や「貸主と借主の信頼関係が破壊された時」に限られるようです。
用法遵守義務違反を理由として、信頼関係が破壊されたかを判断する基準としては、
①契約を結ぶまでの経緯
②貸主と借主の交渉の経緯
③借家に及ぼす影響
④近隣住民への迷惑行為
⑤借主と貸主、両者の事情
などが判例では考慮されています。使用目的違反をしたものの、貸主に大きな不利益をもたらさないこと、現状回復がそれほど困難でないケースでは契約解除が無効となっています。
借主と突然、連絡がつかなくなった!
最近では、孤独死が社会問題になっています。今後、日本が超高齢化社会を迎えることを考えると、賃貸経営者にとって孤独は無縁ではありません。ある日、突然、入居者と長期に渡って連絡がつかない場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。
原則として、経営者が借主の部屋に無断で入ることができるのは、ガス漏れや火災などの「緊急事態」が発生した時だけです。それ以外のケースでは、いくらその物件の経営者といえども、部屋に立ち入ることはできません。もし、このような事実が認められないのに、無断で部屋に入ると、貸主といえども、「住居侵入罪」に問われます。
たとえ、賃貸借契約書に「借主の許可を得なくても部屋に入ることができる」と明記されていても、これは同じです。借主は、「プライバシー権」を有しています。貸主は、この権利を侵すことはできないのです。だからといって現実的に、長期間、生活している様子がない賃借人を放置するわけにはいきません。
このような時には、家賃の滞納も起こっているでしょう。このような場合、借主に対して、ある程度の期間、家賃の滞納が続いていることを理由に賃貸借契約書を解除します。
契約が解除されただけの段階では、貸主は部屋に入ることができません。契約解除後もこの部屋に対して、借主が占有権を有しているためです。さらに、裁判所に明け渡し請求訴訟を起こして、その判決が言い渡され、強制執行が認められた時、やっと部屋に入ることができます。
オーナーからすると、なぜ、自分が所有する賃貸物件に入るのに、こんなに面倒な手続きを踏まなければいけないんだ、と思われるかもしれませんが、現実的にはこの方法でしか部屋に入ることはできないのです。
さきほど挙げた例は、家賃の滞納があったため、契約を解除できましたが、では家賃は支払われているのに、借主が長期間不在の場合はどうでしょうか。このようなケースでも契約解除はできるのでしょうか。
この場合、単に長期間不在にしているという理由だけでは、貸主と借主の信頼関係が壊れたとまではいえないため、契約解除は難しい可能性が高いといえます。長期不在に加えて、家賃の滞納が続いている、あるいは、長期不在により貸主が何らかの損害をこうむっているという場合のみ、契約解除が可能となるのです。
ペット飼育禁止なのに無断で飼っている!
モラル関連のトラブルとしては、「ペット飼育禁止のはずなのに、勝手にペットを飼っている」というケースも多いでしょう。空前のペットブームという時代背景もあり、ペット禁止と知りつつ、犬やネコを飼ってしまう借主は少なくありません。
ペット飼育禁止の賃貸物件では、ほとんどの場合、賃貸借契約書にその旨を記載していることでしょう。問題はそれにより、借主との賃貸借契約を解除できるかどうかです。
結論から言いますと、賃貸借契約のペット飼育を禁止する条項だけでは契約を解除できない、ということになります。
過去の裁判の判例を参考にすると、契約を解除できるケースは、回復しがたい損害を建物や近隣に与えた場合に限定されます。回復しがたい損害とは、ペットの鳴き声で他の入居者に迷惑をかけたり、室内を損壊した時などです。
ただし、過去の判例では、回復しがたい損害がないケースでも特約があれば賃貸借契約を解除できる、とした判例もあります。
いずれにしても、ペット禁止を前提にしている物件なわけですから、「速やかに退去してもらう」、「ペットを飼うのを諦めてもらう」を念頭に借主との交渉を行い、それでも改善されない場合、法的手段をとるのがよいでしょう。
騒音を注意しても一向に直らない!
最近では、モラルが欠如している人が増えているため、身勝手な行動をとる借主も少なくありません。
たとえば、夜中に騒音を出す借主がいた場合、ひと昔前なら、「ご近所から苦情が出ていますので静かにしてもらえますか」と一言いえば済んだのに、最近では、いくら注意しても一向に直る気配がないというケースもあるでしょう。
このようなトラブルを放置すると、他の入居者が退去してしまい空室率を高めるリスクが発生します。また、住人同士の大きなトラブルに発展し、事件になれば、いわくつきの物件として評判を損なうことにもなりかねません。
では、このような話し合いではどうにもならない借主に対して、一方的に契約を解除することができるのでしょうか。
端的にいえば、「賃貸借契約書に禁止事項が明記されていなければ、契約解除することはできない」のが原則です。さきほどの騒音の例でいえば、「他の入居者や近隣に迷惑をかけてはいけない」という文が契約書に盛り込まれていれば、民事裁判で勝訴できる可能性が高いといえます。
また、度を超す迷惑行為なら、契約書に禁止事項が記載されていなくても、民事裁判によって賃貸借契約を解除できる可能性があります。たとえば、近所中に鳴り響くような大騒音、裸で共用部を歩き回るなどがあてはまります。
民事裁判では、迷惑行為の事実を認定することではじめて勝訴できるわけですから、騒音のレベルを専門業者に認定してもらう、などを行っておくとよいでしょう。ちなみに、迷惑行為に対して入居者から苦情が出ているにも関わらず、それを放置すれば、入居者から損害賠償を求める訴訟を起こされる可能性すらあります。
集合住宅経営者の責任として迷惑対策にはきちんとした策を講じる必要があります。
立ち退き料の額は何を基準に決めるべきか
「建物が古くなってきたので建て直したい」、「建物を別の用途で使用したい」といった理由で、入居者への立ち退きを検討するものの、立ち退き料がネックになって話が進展しないという貸主もいらっしゃるでしょう。
まず、立ち退きを求めることが法的にどのような扱いになっているかを見てみましょう。「建物を建て替えざるを得ない理由がある場合」は、立ち退きを求める行為は何ら問題ありません。立ち退きの正当な事由は、借地借家法28条で以下のように定められています。
①貸主・借り主が建物を必要とする事情
②賃貸借に関するそれまでの経過
③建物の利用状況
④建物の現在の状況
⑤立ち退き料などの提供状況
これらの5つが基準となるため、このような場合には正当性がある、ないと断定はしづらいためここでは省略させていただきます。
では、法的に立ち退きの正当性が求められた場合、借り主に必ず立ち退き料を払う必要があるのかを考えてみます。
貸主の中には、立ち退き料は必ず支払わないといけない、と多い込んでいる人もいるかもしれませんが、状況によっては、立ち退き料なしで立ち退きを求めることもできます。
判例を参考にすると、地盤崩壊などの危険性がある建物を建て替えるケースでは、立ち退き料の支払いなしでも明け渡しが正当である、という判決が出ています。
一番気になるのは、立ち退き料の額でしょう。これは何を基準に算出するべきなのでしょうか。
実は、立ち退き料を算出する絶対的な指針は存在しません。
引っ越し費用、貸主・借主の経済状況、建物の老朽度、使用目的などを考慮した上で、貸主が借主に対して立ち退き料を提示し、それが認められれば、ふさわしい立ち退き料となります。
常識的には、明け渡しの事情が極めて私的なもので、さらに、賃貸物件が比較的新しいと、立ち退き料は高額になります。逆に、老朽化がひどく、賃貸物件に危険性があり、早急な立て替えが必要な場合などは立ち退き料は低額になるか、または、支払う必要がない可能性が高いでしょう。
家賃値下げ交渉にどのように対応するべきか
逆に、借主の側から家賃の値下げ交渉をしてくるケースも考えられます。
もちろん、契約時に提示した家賃に納得して入居しているわけですから、頻繁に起こるケースではありません。想定される理由としては、「長期で入居していたので建物が老朽化した」、「周辺環境が著しく悪くなった」などがあげられます。
また、全く同じ条件の部屋の住人に対して、違う家賃を設定していたことを、高い設定の入居者が知ってしまった、というケースもあり得ます。新築時は、15万円に設定していたけど、10年経ったので10万円に下げたというようなケースです。
では、このような家賃の値下げ交渉があった場合、オーナーはどのように対処するのが正しいのでしょうか。この時も、家賃は賃貸人と賃借人の合意によって決まる、という原則は変わりません。
いくら同じ間取りの部屋だからといっても、家賃をいくらに設定するかは、貸主の自由です。一方が安い家賃だからといって、すべての入居者の家賃を同額に統一する必要はありません。そこに、「契約自由の原則」が働いているからです。
オフィスや店舗として貸している場合は、「景気が悪くなったので何とか家賃を値下げしてもらえないか」という相談がありえます。法的にはこれに応じる必然性はありません。
物価指数などの変動があった場合は、借主は貸主に対して、将来の家賃の値下げ交渉をすることができますが、ビジネスがうまくいかないことや不景気は値下げを行う法的根拠になりません。
借主から値下げ要求があった場合の選択肢としては、
① 借主からの値下げを拒否する
② 折衷額で折り合いをつける
③ 借主の要求通りに値下げする
の3つの選択肢があります。
一例として、物件や部屋の一部に瑕疵がある場合の値下げ交渉を見てみましょう。具体的には、建物の一部に瑕疵があるから、それが直るまでの期間家賃を支払わない。または家賃の減額を要求してくるというようなケースです。 このような場合、相手の言い分に法的な根拠はあるでしょうか。
ここでの判断材料は、「貸主と借主の信頼関係が破壊されたかどうか」になります。結論から言いますと、多くの場合、賃貸物件や部屋に瑕疵があったとしても、そのこと自体は値下げ交渉の合理的な理由にはなりません。
ただし、借主から、「生活に支障があるので直してほしい」というお願いがあったにも関わらず、それを放置しておくと、信頼関係の破壊になることが考えられます。
また、たとえば、飲食店にテナントを貸していて、入口ドアや店内の空調に問題があって、営業に支障が出た場合、それによって家賃の値下げはできませんが、損害賠償請求権は生じます。
瑕疵があった場合、放置することは貸主、借主の両者に何のメリットをもたらしません。速やかに修繕して安定的な信頼関係を継続するのが望ましいでしょう。
家賃の値上げ交渉をどのように行えばいいか
ここまでお話してきたように、家賃の支払いの遅れや修繕費がかさむなどのリスクがあることで、実際に賃貸経営をしてみると、期待していた利回りが得られないというケースもあります。
また、長期で経営をしていると、物件の周辺に、駅や道路が新設されたり、大型ショッピング施設ができることで、土地の価値が上がることも考えられます。さらに、不動産会社の意見などを参考にして家賃を設定したものの、後でご自身の物件の家賃が安く設定されていたことに気づくこともあるでしょう。
そんな時、貸主の脳裏に、「家賃をもっと上げられないか」という考えがよぎることもあるでしょう。
しかし、借主とどのような交渉をしていいのか分からずに、現状維持のままになっていることも少なくないはずです。また、強引に家賃を上げる交渉を行ったことで、入居者とのトラブルに発展することもありえます。
そのような現実面を克服して、家賃を値上げするにはどうしたらよいでしょうか。
そもそも家賃とは、オーナーと借り主の合意によって決まるものです。この条件で○万円と広告を出し、それを借主が見て承諾し、最終的に賃貸借契約書を交わすことで家賃が確定します。合意によって決まるものですから、契約時に借主が値下げ交渉をしてくることもあります。
逆に言うと、合意さえできれば、契約中や更新時でも家賃の値上げはできるわけです。
とはいうものの、家賃の値上げは借主にとって、生活に直結する重大なことです。
一方的かつ強引に「家賃を値上げします」と告げられても、到底納得できることではありません。そのような相手の感情も慮りつつ、家賃の値上げの理由を懇切丁寧に説明し、借主との合意を目指してください。一度で合意が得られない場合は、数回に分けて対話を重ねるのも一案です。
いくら話し合いを重ねても、借主が家賃値上げを認めない。しかし、賃貸人としてはどうしても家賃を上げなければならないという場合は、「調停」による話し合いを行います。
調停では、貸主と借主の間に第3者が入って話し合いによる解決策を見い出します。第3者は、裁判官と調停委員から構成される調停委員が担当します。調停はあくまでも話し合いの場ですから、解決策が出ない場合は「訴訟」を起こして、民事裁判で家賃の値上げを目指すことになります。
家賃交渉で訴訟を起こすと、必然的に弁護士費用がかかります。加えて、家賃値上げ交渉の場合は、不動産鑑定士に依頼して適正な家賃を算出してもらう必要があります。弁護士と不動産鑑定士に支払う費用を考慮すると、家賃の安い物件では裁判を起こしても採算が合わないケースが大半です。ですから、ある程度の額の家賃の物件のみ、訴訟をおすすめします。
ちなみに、将来の家賃の値上げ交渉に備えて、賃貸借契約書に「自動増額条項」を盛り込んでいるという方もいるでしょう。自動増額条項は、一定期間ごとに一定の率で家賃が上がっていくことを予め契約時に借主に伝えるものです。
自動増額条項があるから安心、という方もいるかもしれませんが、自動増額条項があっても、合理性がなければ家賃の値上げは法的に有効ではありません。つまり、訴訟を起こしても必ずしも勝訴できるわけではないのです。この条項があることで、家賃の値上げ交渉がしやすくなるという効果は見込まれますので、契約書に入れておくこと自体は良いでしょう。
貸主にどこまで修繕の義務があるか
実際に賃貸物件を経営して分かることは、修繕費の費用が意外にかかるということでしょう。
ある程度の部屋数の物件の経営をしている経営者のもとには、「水道の蛇口のしまりが悪い」、「お風呂の調子が悪い」、「雨漏りがする」、「たてつけが悪い」、といった、入居者からの苦情が頻繁にくるはずです。特に、最近の入居者は、サービスに対する要求が高くなっているので、細かい苦情が増えていることと思います。
これらにすべて対応していたら、意外に手元にはキャッシュが残らない……ということでお悩みの方も多いでしょう。特に築年数が経った物件では、空室を埋めるために家賃を上げられない、それなのに、修繕費はかさむ一方、という状況に陥る方もいらっしゃるはずです。
少しでも修繕費をおさえるための策としては、蛇口のパッキンなどのような小さな修繕は「借り主が行う」と賃貸借契約書に予め明記しておくことです。
しかし、費用のかかる大きな修繕に関しては、貸主に修繕する義務があることが法的に定められています。
もし、貸主が借主の生活に支障が出るような雨漏りなどの修繕の義務を果たさない場合、「家賃を不払いにする」、「家賃を減額して支払ってくる」といった手段に出てくることも考えられます。また、我慢できなくなった借主が自分で業者に依頼して修繕を行い、かかった費用を貸主に請求してくる可能性もあります。
これらのことを考慮すると、貸主にとって修繕を放置するメリットは何もありません。放置するのはトラブルのもとですので、速やかな修繕を行うのが得策です。
もし、建物が老朽化して、採算と修繕費が見合わないのであれば、リフォームや立て替えを行い、経営計画を見直すのも一案です。
例外的に、貸主の修繕義務が除外されるケースとしては、修繕にあまりにも多大な費用がかかる場合です。とても採算がとれないような大きな修繕に関しては、必ずしも修繕しなくてもよいという判例が出ています。
だからといって、その事実をそのまま借主に伝えてもなかなか理解は得られないでしょう。このような場合、一方的なコミュニケーションにならないよう、丁寧に借主に伝えていくことが大切です。たとえば、完全に直すと多大な費用になってしまうため、応急処置的な修繕で納得してもらえるよう粘り強く交渉するといった具合です。
借主が蒸発した時、妻に家賃を請求できるか
たとえば、契約をしている借主本人が蒸発し、その妻が残された場合、妻に対して家賃は請求できるでしょうか。
これは現実的にあり得るケースです。家賃が支払われないな、と気づいて部屋を尋ねると、奥さんが出てきて、「主人が家に戻らなくて……」との対応。いくら家賃を払うように言っても、「主人が戻らないと何も分からない」の一点張りというような具合です。このようなケースでは、配偶者に対しては家賃を請求できます。
これは、日常家事債務に関して夫婦には連帯責任がある、と民法で定められているからです。夫婦が連帯責任を負う理由としては、結婚生活の費用は夫婦で分担するという考え方が挙げられます。そうであるなら、滞納した家賃を連帯責任で支払うのは合理的と言えます。妻にこのような背景を丁寧に説明し、きちんと支払うよう求めていきましょう。
家賃の回収について、違うシチュエーションで考えてみましょう。
では、借主が死亡した場合はどうでしょうか。発生している家賃や滞納している家賃は誰に請求すべきでしょう。このようなケースでは、少々複雑になります。
基本的には、家賃の請求相手は、「相続をした相手」です。多くの場合、相続人は複数になります。法定で定められた相続分に従い、家賃を支払う義務があるわけです。この法律に基づいて請求を行うと、配偶者にいくら、千葉県に住んでいる長男にいくら、宮城県にいる次男にいくら、と複数の相続人を相手に家賃の支払いを求めていくことになります。
これはとても現実的とはいえません。相続人の代表を決めてもらい、その方に対して家賃を請求するのが望ましいでしょう。