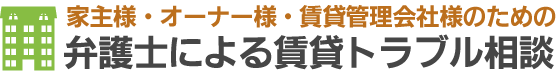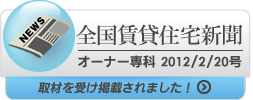「従来の賃料なら払う」と言われたが…
![]()
家賃の値上げ要求をしたところ、断られました。今までと同一額での家賃を納める旨の申し出がありましたが、これは拒否しています。借主は「今まで通りの額であれば支払う意思はある」と言っています。私の対応がまずく” 家賃を支払えないのは貸主が受け取らないことに原因があるので、このまま支払う必要はない”と受け取られていないか心配です。
「供託」をされると、家賃を支払ったことになってしまう
質問は「家賃の値上げに応じない入居者との間で契約を解除できるか?」ということでしたから、その入居者が家賃の支払いを拒むのであれば、解除は可能ということになります。
ただし、借主が「供託」という手続きをとった場合、契約の解除はできません。供託は、簡単に言えば、家賃を第三者(国)に預けることで、家賃を支払ったのと同じ効果を持たせる手続きのことです。
よって、いくら納得できない額でも、借主が「供託」という法律的な手続きに則り、支払いを行う限りは、貸主側は一方的に契約の解除はできないのです。
家賃滞納などの賃貸トラブルの解決法をまとめた無料小冊子
「賃貸トラブル解決法 知らなきゃ損する10のポイント」をご用意いたしました。
詳しくはこちらからご確認できます。
新家賃額が決定するまでの家賃の扱い
貸主が家賃の値上げを要求する場合、新しい家賃の額は、先に述べたように、当事者同士の話し合いか、調停または訴訟という手続きを経て確定します。
ただし、その確定までには、少なからぬ時間がかかります。この間、借主側もいくら家賃を支払えばいいのか迷うかもしれません。
この点について、法律では「裁判で新家賃額が確定するまでは、借主は相当と思われる額を家賃として支払えば足りる」としています(借地借家法32条2項)。「相当と思われる額」とは、それまでの家賃額と理解すればいいでしょう。
その後、新しい家賃の額が確定し、借主が支払っていた額がその額に満たない場合は、不足分に年1割の遅延損害金を加えた金額を支払ってもらうことになります。
もっとも、このような手順で借主が家賃を支払おうとしても、貸主のなかには、値上げした家賃額でなければ受け取りたくない人もいるかもしれません。
その結果、借主が家賃を支払わなければ、家賃の不払いを理由に賃貸借契約の解除が可能となります。
「自動増額条項」を盛り込もう
家賃増額の訴訟が貸主にとって採算があわない場合、家賃を増額させる「別の方法」を検討することが必要です。
例えば、一定期間ごとに定率で家賃が増額する旨の特約「自動増額条項」を契約書に盛り込む、などです。
「借地借家法」では、借主に不利な条項は無効とされますが(借地借家法30条)、増額率が固定資産税の上昇率によって決められるような合理的な内容であれば、有効とみなされます(自動増額条項を有効と判断した判例として東京地裁昭和56年7月22日判決)。
もっとも借主が、自動増額条項自体が有効かどうかを問題にして、家賃の値上げを拒否した場合、貸主としては結局訴訟を提起せざるを得なくなります。
しかし、このような条項があることで、借主が家賃の値上げを拒否することは減少すると思われるので、意味がないわけではありません。
家賃増額訴訟の採算性は
貸主が、家賃の値上げを要求して訴訟を起こす場合、事前に考えるべきことがあります。それは、そもそも裁判をして採算がとれるのか、ということです。
訴訟には、時間、お金などのコストがかかることを覚悟しなければなりません。家賃増額訴訟であれば、弁護士費用や、不動産鑑定士に支払う費用などが必要です。このうち不動産鑑定士に支払う費用は、十数万円から、場合によっては数十万円になると考えておくのがよいでしょう。
このような多額の費用がかかりますから、値上げが最終的に認められても、裁判費用を考慮すれば、「かえって損をした」ということになりかねません。家賃が安い物件の場合、こうした事態に陥りやすいといえるでしょう。
訴訟を起こす際には、このように採算がとれるか否かを見極める必要があるのです。
「調停」と「訴訟」
調停では、裁判官と調停委員から構成される調停委員を交えながら、当事者同士で話し合うことになります。経験豊富な調停委員が第三者としてアドバイスすることで、当事者のみでは合意に至らなかった協議が収束することが期待されているのです。
調停はあくまで話し合いでの解決なので、当事者同士の譲り合いが必要です。ですから、借主・貸主ともにまったく譲歩しない場合には、調停での解決は困難となります。
調停で解決できない場合、貸主は、訴訟を起こして家賃の値上げを求めることになります。訴訟では、不動産鑑定士の鑑定などをもとに、最終的に裁判所が適切な家賃を定めることになります。
まずは話し合いを
![]()
原則として家賃は、貸主と借主、両者の合意によって決まります。貸主が一方的に家賃を値上げすることはできないので、貸主は借主と家賃について話し合わなければなりません。
この話し合いを通じて両者の間で合意が得られれば、いつでも家賃を値上げすることができます。反対に、合意できない場合には、法的な手続きをとることになるでしょう。
法的手続きには調停と訴訟があります。調停とは、裁判所において、当事者同士が話し合い、合意に達した場合に「調停調書」という公的な和解書類を作成する手続きのことです。一方、訴訟とは、裁判所に対し、判決を求めて訴えを起こすことです。
こうした一連の手続きのなかで、「言った」「言わない」という議論にならないためにも、貸主側は、法的手続きをとる前に配達証明付き内容証明郵便で、家賃をいくら増額するのかについて明確に意思表示をしておきましょう。
ただ、貸主側がこうした手続きを一方的に進めると、借主との間で感情的な対立に発展することも考えられます。法的な手続きをとる前に、話し合いでの解決が不可能かどうか、よく検討してみてください。
値上げに応じようとしない入居者への対処法
![]()
マンションの家賃を10%値上げしたいと考えています。しかし、入居者のなかには値上げに絶対応じないと主張する人がいて困っています。値上げを拒否する入居者には、契約を解除して出ていってもらいたいのですが、可能でしょうか。
はじめに
家賃は借主、貸主双方にとって重要な問題です。また、契約更新は、貸主にとって関心の高い事柄でしょう。借主が貸主から家賃の値上げを言い渡されたとき、あるいは貸主が契約を更新したくないときは、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか?
ここからは、オーソドックスなトラブル事例とその対処法をQ&A方式で紹介していきます。
原則として貸主に損害賠償責任はない
![]()
借主の財産は、基本的に財産を管理している借主自身が守るべきでしょう。
賃貸借契約上、貸主には借主の財産を盗難などから保護する管理義務はありません。ですから、原則として、貸主が借主の盗難被害の損害賠償責任を負うことにはならないのです。
もっとも、契約によっては、貸主がこのような管理義務を負担しているといえる場合もあり、その場合には、貸主は借主が被った盗難被害について、損害賠償責任を負います。
具体的にどのような場合に損害賠償責任を負うかは、貸主がどの程度の管理義務を負担しているかによって異なるため、個別の賃貸借契約の事情に応じて、ケースバイケースで判断されます。
ピッキングによる盗難被害について、貸主の管理責任が問われた過去の裁判でも、「賃貸借契約において、貸主が負うべき本来的義務は、借家を使用収益させる義務、修繕義務などであって、借主の所有財産を盗難などから保護することを内容とする管理義務は賃貸借契約から当然に導かれるものではない」とし、貸主がこのような管理義務をどの程度負うかは、個々のケースに応じて判断されるべきだとしています(東京地裁/平成14年8月26日判決)。
先ほど紹介した東京地裁は、盗難被害について貸主は責任を負わないと契約に記載されていること、賃貸事務所の入口はダブルロックで一応の防犯効果が期待できたこと、貸主が順次賃貸ビルに機械警備を導入している最中であったこと、さらに借主が貸主にカギの交換を求めたことがなかったことなどを理由に、貸主はピッキング被害防止策をとる義務を負担していなかったとして、損害賠償責任を負わないと判断しています(同判決)。
以上をまとめると、原則として、借主がピッキングによる盗難被害に遭ったからといって、貸主はその損害を賠償する責任を負わなくてもいいと考えるべきでしょう。
もっとも、貸主がピッキングによる盗難被害について警察から何度も指導を受けていたのに十分な盗難防止策をしていなかったという場合には、事情が違ってきます。
この場合は、盗難を未然に防ぐ措置を怠ったわけですから、貸主は損害を賠償しなければならないでしょう。