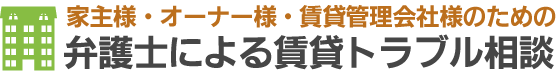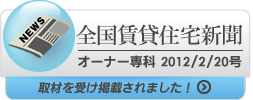契約解除が認められなかったケース
決められた使い方を守らなかったり、無断で増改築がなされたりしても、増改築をするに至った経緯や程度、建物の構造、原状回復の難易度などを考慮して、「信頼関係が破壊されていない」と判断したケースもあります。
1.必要にせまられたケース
たとえば、借主が物件に新たな外壁とシャッター4基を無断で設置し、さらに壁面(一部)や天井を撤去するなど、かなり大幅な増改築を行ったという事案がありました。
この増改築は貸主に無断で行われたものでしたが、裁判所は信頼関係が破壊されていないとして契約の解除を認めませんでした。その理由として、この増改築が、通行人への危害防止や雨漏り防止などで行われたもので、緊急性、必要性、合理性が認められること、新たに設置された部分は、基礎の撤去がそれほど難しくなく、物件の使用に関して違反がなかったということが挙げられます(東京地裁/平成6年12月16日判決)。
2.物件の構造を変更しないケース
賃借物件の裏の空き地にバラック風の仮建築物を無断で建て、この建物に自由に行き来するために賃借物件の壁を撤去したというケースもあります。このケースについても、裁判所は解除を認めていません。
増築部分が賃借物件の構造を変更しないで付け加えられたものであり、1日で撤去できる程度のものだったこと、また、賃借物件が、貸主が修理をしない代わりに借主側の負担で必要に応じて改造できるという取り決めで借り受けたものだった、というのが主な理由です(最高裁判所昭和36年7月21日判決)。
以上をまとめると、たとえ借主が無断で増改築をしたり、使用目的を守らなかったりしても、実際に契約を解除できるかどうかは信頼関係の状況次第ということになります。
そして、これについて判断するには、増改築の経緯や程度(建物の基本的な部分かどうか)、建物の構造、原状回復の難易度などが重要な要素になってくるのです。
契約解除が認められたケース
借主が無断で増改築を行い、それにより信頼関係が損なわれ、契約解除は止むを得ないと裁判所が判断したケースとして、他にどんなものがあるでしょうか?
過去の判決を確認してみましょう。
1.信頼関係の破壊が認められたケース
借主が、それまで入口として使用していたドアを閉ざし、別の壁に入口をつくったほか、内装クロスの張り替え、カウンターの取り替え、電気照明などの内装工事を無断で行った事案に対して、信頼関係の破壊が認められています。このケースでは、店舗の基本的な部分に改変が加えられたこと、借主が貸主に改造のための承諾を求める働きかけすらしなかったことなどが考慮されています(大阪地裁/昭和50年9月26日判決)。
2.改装の「範囲」が争われたケース
借主がファッション関係の店舗からアイスクリーム販売店へ業種を変更したのですが、そのことを貸主に隠し、合意した範囲を大幅に超えて改装を行ったという事案です。改装は、窓、天井、床、壁をすべて取り外した大規模なものでした。
借主は、「改装が賃借部分の基本構造に変更を加えるようなものではなく、将来の修復が可能である」と主張していましたが、裁判所は、仮にそうだとしても、借主が業種の変更を隠したまま、従来の業種のままで改装をすると貸主に信じ込ませたこと、また、改装の範囲について文書を作成して合意したのに、これに違反したことを重視して、信頼関係の破壊による契約解除を認めました(東京地裁/平成元年1月27日判決)。
「信頼関係の破壊」によって契約の解除は可能
![]()
このケースでは、借主がキャバクラの営業をするために無断で増改築を行っています。
賃借物件の所有権は、一般的には貸主が持っていますから、借主が無断で改造することは許されません。
そこで通常、賃貸借契約書では、増改築のためには貸主の承諾を必要とし、これを得ずに無断で増改築した場合や、あらかじめ決められた使い方を守らなかった場合には契約を解除できるという特約が定められます。
本事例のような場合でも、このような特約に基づいて契約解除を主張できるでしょうが、解除できるかどうかは、最終的に信頼関係が破壊されたか否かによります。
たとえ家賃の不払いが続いても、信頼関係が破壊されたといえなければ契約を解除できないのと同様に、用法遵守義務違反や増改築禁止違反の行為があっても信頼関係が破壊されていなければ、一方的に解除をすることはできないのです。
本事例では、キャバクラとスポーツ用品店の店舗兼事務所とでは業態が大きく異なること、また、借主がキャバクラ営業の目的を隠していたことが明らかですが、これは当事者双方の信頼関係に重大な影響を及ぼすものです。
さらに、キャバクラを営業するために、室内にさまざまな設備の増改築が行われたことが考えられるので、信頼関係が破壊されているとして契約解除は有効だと考えられます。同様の事案においても、裁判所は解除を認めています(東京地裁/平成3年7月9日判決)。
無断で増改築したうえキャバクラ経営を始めた借主
![]()
所有するビルの1室を、スポーツ用品店の店舗兼事務所という使用目的で貸しました。ところが借主は、ビルを無断で改造し、その場所でキャバクラの営業を始めたのです。
部屋の使用法が契約で決めたものとは明らかに異なりますし、無断で増改築をしているので、このことを理由に契約を解除できないでしょうか。
使用目的を守らなかったことで信頼関係が破壊されたか
用法遵守義務違反を理由として信頼関係が破壊されたかどうかについて、判例は、
①契約を結ぶまでの経緯
②用法遵守義務違反に関する貸主と借主間の交渉の経緯
③用法遵守義務違反が借家に及ぼす影響の程度
④近隣住民への迷惑の有無・程度
⑤貸主・借主双方の事情
などを総合的に考慮して判断していると考えられます。
質問のケースでも、これらの事情を総合的に考慮したうえで、信頼関係が破壊されたかどうかが判断され、その結果によって契約解除が有効かどうかが決まることになります。
なお、質問のケースと同様の事例として、東京高裁の昭和50年7月24日判決があります。
この判決は、学習塾の生徒数がわずか6名にすぎないこと、借主は塾に使用する6畳間にじゅうたんを敷いて汚さないように配慮したこと、学習塾開設から解除通知までわずか2カ月でその間建物に毀損があったとは認められないこと、さらに借主が、その後学習塾を廃止して建物を住居専用に使用していることなどから、信頼関係の破壊に至っていないとして、契約解除を無効としました。
用法遵守義務違反が争点となった判例
用法遵守義務違反による契約解除が問題となった事例では、契約解除を無効とした判例と有効とした判例があります。
1.契約解除を無効とした判例
この判例では、借主がそれまで活版印刷の工場兼事務所に使っていた建物を、写真印刷の製版のための作業所に変更したことに対し、貸主が契約を解除したことが有効かどうかが争われました。
この点、東京地裁は、写真印刷の製版作業は活版印刷作業よりも静かで清潔な作業であり、貸主に不利益を及ぼさないこと、写真印刷の製版作業に変更したのは借主に止むを得ない事情があったこと、また、原状回復はそれほど困難ではなく建物に重大な影響を及ぼさないなどの理由から、信頼関係破壊に至っていないとして、契約解除を無効としました
(東京地裁の平成3年12月19日判決)。
2.契約解除を有効とした判例
この判例では、会社の事務所に使用するために借りたビルの一室を、借主がテレホンクラブの営業に使用したことを理由とする契約解除が有効かどうかが争われました。
東京地裁は、借主の営業によりビル全体の品位が損なわれ、警察の捜索を受けるなどビル所有者として好ましくない事態が生ずる恐れがあること、契約を結ぶ際に借主がテレホンクラブを営業することを隠しており、それがわかっていれば貸主は物件を貸さなかったこと、また、他の入居者からも苦情が出ていることなどから、信頼関係が破壊されているとして契約解除を有効としました(東京地裁の昭和63年12月5日判決)。
このほかに、契約解除を有効とした判例としては、貸室を暴力団の事務所として使用したことが背信行為であるとして、解除を有効とした判例(東京地裁/平成7年10月11日判決)があります。
学習塾としての使用は用法遵守義務違反
![]()
賃貸借契約は、通常、使用目的を定めて結ばれるものであり、借主は、その目的に従って物件を使用しなければいけません。これは用法遵守義務というものでした(民法616条、594条1項)。
契約書に「借家は住居のために使用すること」と記載されているのに、学習塾として使用している場合には、借主が用法遵守義務に違反していることになります。
では、この用法遵守義務違反を理由として、貸主は、直ちに契約を解除することができるでしょうか。
この場合でも、判例は、貸主・借主間の信頼関係が破壊されたかどうかを問題とします。つまり、借主が用法遵守義務に違反する行為を行った場合でも、お互いの信頼関係が破壊されたといえなければ、契約解除はできないのです。
入居者が無断で塾経営
![]()
住居として家を貸したところ、入居者がその借家で学習塾を経営していることがわかりました。契約に違反していることは明らかなので、契約を解除して出ていってもらいたいと考えていますが、可能でしょうか?
法的手続きをとって入室する
では、借主が3カ月家賃を滞納していることを理由に、賃貸借契約を解除したうえで、立ち入るのはどうでしょうか。
家賃の滞納で信頼関係が破壊されたと言えれば、賃貸借契約を解除することは可能でしょう。契約が解除されれば、借主は賃借権を失いますから、貸主は借主の承諾を得ずに室内に立ち入ることができそうです。しかし、たとえ賃貸借契約を解除したとしても、借主は、依然として貸室について「占有権」を持っています。
結局、賃貸借契約を解除しても、貸主が無断で部屋に立ち入ることは、借主の占有権を侵害することになるので、やはり原則として許されないことになります。
事実上物を支配している状態のことを占有権と言います。法律では、物を事実上支配している状態について一定の保護をしているのです。ここでは、貸室に住んでいることで、貸室を事実上支配していると言えるため、貸室に対する占有権がある、というのです。
もっとも、質問のケースでは、借主が3カ月間も貸室を留守にしているわけですから、承諾をもらうのは不可能だといえます。
このような場合に貸室内に立ち入るためには、まずは借主を相手方として賃貸借契約を解除したうえで、裁判所に、貸室の「明け渡し請求訴訟」を提起すべきです。
そして、裁判所から判決を言い渡してもらったうえで、さらに裁判所に強制執行の申し立てをし、この手続きの流れのなかで室内に立ち入るようにしましょう。
このような法的手続きを踏めば、たとえ借主の承諾がなくても、合法的に部屋の中に立ち入ることができます。
緊急事態が発生した場合は?
火災などの緊急事態が発生している場合、貸主は、「緊急事務管理」として、承諾を得ないで部屋の中に入り、ガスや水道の元栓を閉めたり、消火活動をしたりするなど、適切な措置をとることができます。
事務管理とは、他人の事務(仕事)を処理する義務がなくても、当人に代わって処理することをいい、他人の財産などに緊急事態が発生している場合、これを防ぐために処理することを緊急事務管理といいます。
質問のケースでは、借主は3カ月も家賃を支払わずに部屋を留守にしており、「何かあるのでは?」と考えてしまうのも仕方ない状態にあるといえます。しかし、室内でガス漏れや水漏れ、火災などの緊急事態が発生しているとまでは言えないでしょう。
したがって、緊急事務管理とは認められず、やはり借主の承諾を得ないで勝手に部屋の中に立ち入ることはできません。