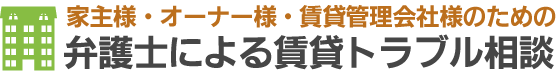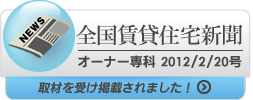無断で室内に入ることは許されない
![]()
まず、賃貸借契約が継続している間は、借主は貸室を使用する権利を有しているという原則があります。ですから、たとえ貸主であっても、借主から承諾を得ない限り、原則として室内に立ち入ることはできません。借主から承諾を得ないで勝手に合カギを使って部屋に立ち入ると、住居侵入罪(刑法130条)という犯罪に問われてしまいます。
なかには、契約書に「貸主は、必要がある場合には、借主の承諾なく貸室内に立ち入ることができる」という条項が設けられていることがあります。
このような条項を設けていれば、室内に立ち入られることを借主があらかじめ承諾していたとみなし、貸主は勝手に室内に入ることができるように思えます。しかし、賃貸借契約書のなかで、いくらこのような条項を設けていても、貸主が室内に立ち入る際には、原則として、借主の承諾を得ることが必要です。
貸室は借主にとって極めてプライベートな空間です。このような条項を設けたからといって、貸主が借主のプライバシー権を奪うことは許されません。
家賃滞納のうえ長期留守なら可能か
![]()
マンションの入居者が、3カ月間も家賃を支払わずに部屋を留守にしています。室内がどうなっているのか心配なので、一度合カギで開けて点検したいと思っているのですが、承諾をもらわずに貸室に立ち入っても大丈夫でしょうか。
連帯保証人に対する請求はどうする?
1.まずは借主本人に支払いを督促
賃貸借契約を結ぶ際には、通常、連帯保証人がつけられます。ですから、貸主は法律上、連帯保証人にも滞納家賃を請求することができます。
とはいえ、借主側としては家賃を滞納している事実を知られたくないでしょうから、いきなり連帯保証人に滞納家賃を請求されることを快く思わないでしょう。場合によっては、感情的になって話し合いがうまくいかなくなるかもしれません。
ですから、まずは借主本人に支払いを督促すべきです。そこで「連帯保証人の方にも連絡します」といえば、借主は家賃滞納の事実を知られまいと真剣に金策するかもしれません。
2.法的な措置に移行
話し合いで借主本人、連帯保証人から家賃を回収できない場合、法的な措置に移行
話し合いで借主本人はもちろん、連帯保証人からも家賃を回収できなければ、あとは法的な措置に移行します。この場合は先に述べた民事訴訟に加え、連帯保証人にも滞納家賃の支払いを求めて、借主と連帯保証人を、両方一緒に被告として提訴することになります。
支払いの約束を書面で残しておく
1.相手が滞納家賃を支払うと約束してきた場合、書面に残しておく
貸主側の働きかけによって、相手が滞納家賃を支払うと約束してきた場合には、その可能性が低くても、必ず念書や確約書などの書面に残しておくべきです。
たとえば「私は、貴殿から賃借している○○マンション○号室の滞納家賃○○円を、○○までに○○の方法で支払うことを約束し、これに反した場合は、何ら催告なく賃貸借契約を解除されても異議はなく、この場合ただちに本件建物を明け渡します」という文言を入れた念書を取っておくのです。
契約の解除が有効だと認められるためには、信頼関係の破壊があったという事実が必要ですが、滞納家賃の支払いを約束しておきながらそれを破ったということになれば、信頼関係の破壊の裏付けになるからです。
2.それでも借主が催告に応じない場合
早期に民事訴訟を提起して、明け渡しと同時にこれまでの滞納家賃と解除後の使用料を損害金として請求することになります。
もちろん、訴訟を提起したからには裁判所を通じて最終的な解決を求めることが第一の目的ですが、通常の借主は、裁判にかけられるだけ(あるいは訴状を受け取るだけ)でも心理的に追い込まれます。何とかして明け渡しを阻止しようと、真剣に金策をするかもしれません。
3.訴えを起こしても借主が滞納家賃を支払わない場合
訴えを起こしても借主が滞納家賃を支払わず、裁判でも貸主が勝訴した場合は、強制的に家賃を支払わせることになります。
借主が部屋を明け渡し済みであれば、強制執行により滞納家賃の支払いをさせることが可能です。また、明け渡さずに居座り続けるのであれば、強制執行によって滞納家賃の支払いと明け渡しを実行することになります。
法的措置の可能性を示す
![]()
家賃の支払いは、賃貸借契約における借主の最も基本的な義務ですから、借主がこれを怠った場合には、「賃料の不払い」を理由として契約解除をすることが可能です。
そこで貸主としては、家賃の滞納があった場合、ただちにこれを支払うように催告をして、解除の準備をすることができます。
借主のほうでは家賃を支払う工面がついているのに、貸主側は何もしないだろうと甘く見て支払いを渋っているだけかもしれません。そうであれば、催告をすることで契約解除やこれによる明け渡しを避けるために、直ちに賃料を支払ってくる可能性は十分あります。
契約解除や強制執行による明け渡しの可能性を示されると、たいていの借主は驚き、こうした手続きをとられることを恐れるでしょう。ですから、借主に危機感を抱かせる意味でも、法的手続きについて触れながら支払いを促すことは有効な手段です。
なお、このとき、支払いについては、一定の期限(たとえば1週間以内)を設定しておきましょう。
Point:催告は必ず配達証明付 内容証明郵便で
裁判の証拠とするために、最終的に契約を解除して明け渡しを求める場合には必ず内容証明郵便にするべきです。
ただ、最初の段階では面談や普通郵便で通知したほうが無難です。いきなり内容証明郵便を出すと相手を刺激することになりますし、結果的に態度を硬直化させて話し合いがうまくいかなくなることも予想されるためです。
もっとも滞納家賃が増えれば増えるほど回収が難しくなるのですから、最初の催告は早めにしておくべきでしょう。
どのような回収方法がある?
![]()
アパートの一室を貸していますが、借主が2カ月連続で家賃を滞納しています。この滞納家賃については、どのように回収していけばよいでしょうか。また、連帯保証人になっている人に対しては、どのようにして滞納家賃を支払ってもらえばよいでしょうか。
契約書に「催告不要」の特約があったら
借主に対して家賃の督促をしなくても、貸主側が一方的に契約を解除できることが契約書に明記されている(無催告の特約)場合はどうでしょうか?
結論から言えば、いくら契約書に「催告不要」と書いてあったとしても、催告の手続きはしておいたほうがよいでしょう。
判例では、このような取り決めは「催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合」にのみ有効としています(最高裁判所/昭和43年11月11日)。
言い換えれば、一方的な契約解除は、それが止むを得ない特殊な事情以外は原則として無効だということです。
ですから、貸主が契約を解除する場合には、ある一定の期間を定めて、その期間内に家賃を支払うよう借主に請求することが望ましいのです。
この場合の「期間」とは、通常1週間程度を定めれば問題ないでしょう。
なお、家賃の請求や契約解除の意思表示をしたことは、裁判のときに貸主側が証拠を提出しなければいけません。そこで、配達証明付内容証明郵便で、「この書面受領後、1週間以内に未払い賃料○○○円が支払われない場合は、賃貸借契約を解除するとの意思表示をします」という書面を入居者に郵送しておくことが必要となります。
「信頼関係の破壊」の判断基準
賃貸借契約を解除するためには、信頼関係が破壊されたという事実が必要になります。
建物の賃貸借契約は、売買契約のように、何かを売ってもらう代わりにその代金を支払うというような1回限りの関係ではありません。普通は契約が数カ月から数年間続くことが想定されるので、そのためには両者の信頼関係が不可欠です。これを解除するためには、信頼関係が破壊されたという事実が必要になるのです。
多くの裁判例では、賃料不払いが当事者間の信頼関係を破壊するような不誠実なものでない限り、契約を解除することは貸主と借主の間の信義に反し、許されないとされています。
そして、信頼関係の破壊については、不払いの理由、不払いの金額、不払いの期間、一旦は不払いがあってもその後法務局に対して供託の手続きをし続けているか、などさまざまな事情を考慮して裁判所が判断することになります。
したがって、質問のケースのように3カ月分の未払いがあったとしても、貸主側の望む契約解除が認められるとは限りません。
しかし、借主に未払い分の家賃を払おうという誠意がまったくなく、止むを得ないような理由(高額な治療費を支払うためにどうしても払えなかったなど)がなければ、未払い分の賃料を請求(催告)したうえで解除が認められる可能性は高いでしょう。
借主の基本的な義務「家賃の支払い」
![]()
借主が家賃を支払うことはもっとも基本的な義務です。賃貸借契約は、貸主が部屋や建物などを貸し、借主がその対価として賃料を支払う契約であるためです。
この義務が守られず、家賃を支払わないまま借主が居座り続けると、貸主にとっては大きな損害になります。こうした損害が発生しないように、「一度でも賃料の支払いを怠ったときは催告(督促)なしに契約を解除できる」と前もって契約書に定めておくことは、よくあることでしょう。
とはいえ、借主も生活のためや事業のために部屋を借りているはずですから、どうしても家賃が払えなかったという場合に、即刻出て行かなければならないとなると、大変困ったことになります。
そこで判例では、いくら契約書で取り決めがあったとしても、たった一度の家賃の不払いがあっただけでは、契約の解除はできないという扱いがなされています。
では、具体的に何回の不払いがあれば契約を解除できるのでしょうか?
実は、この点について確固とした基準があるわけではありません。
これまでの裁判例を見ても、2カ月間の賃料未払いがある場合に解除が有効とした例(松山地裁/昭和31年9月18日判決)もあれば、7カ月分の賃料未払いがあっても解除が認められなかった例(神戸地裁/昭和30年1月26日判決)もあります。
一般的には、契約の解除が成立するためには、何回かの賃料不払いがあったことが前提となります。解除できるかどうかの決め手となるのは、「当事者間の信頼関係が破壊されているかどうか」にかかってきます。
滞納1カ月で契約解除は可能?
![]()
マンションの一室を貸していますが、入居者が3カ月連続で賃料を支払ってくれません。賃貸借契約書には、「1カ月でも賃料の不払いがあった場合は、催告なしに賃貸借契約を解除できる」という一文があります。契約を解除して出て行ってもらうことはできるのでしょうか?