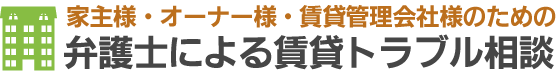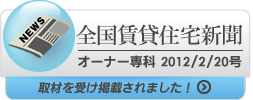クロスの価値は入居後4年で60%減少する
では、質問のケースについては、どう考えればいいのでしょうか。
物的範囲について、ガイドラインの基準に従うと、借主は原則として部屋全体のクロスを張り替える必要はなく、キズを含む面の張り替え費用を負担すればよいことになります。
次に経過年数ですが、借主が入居した時点でクロスが張り替え後何年経過していたのかは明らかではありません。
しかし、新品の状態であったとしても、ガイドラインの基準によれば入居後4年間でクロスの価値は60%減少していることになります(15%×4)。したがって、借主へ請求できるのは、張り替え対象部分の修繕費用のうちの40%が上限ということになります。
このように、借主に原状回復費用を負担してもらう場合には、「物的範囲」と「経過年数」が問題となります。請求する原状回復費用が適切な額かどうかを検討するにあたっては、この2つの点に注目するようにしてください。
物的範囲と経過年数
![]()
クロスとは、壁や天井などに張るビニールなどの内装材のことです。
引越しの荷物の搬送時についたキズは、借主が粗暴な使い方をして発生したため、クロスの修復費用を請求できます。
では、借主は、キズのあるクロスの一部分のみ修復して新しいクロスにすればよいのでしょうか。それとも、キズのある部分のみ新しいクロスとすると、他の古いクロスとの関係で部屋全体の調和がとれなくなるので、天井なども含め部屋のクロス全体についての修復費用を負担しなければならないのでしょうか。このような修復対象物の範囲の問題を「物的範囲」の問題といいます。
また、クロスは入居時から4年経過しています。貸主は時間の経過にかかわらず、張り替え部分についてクロス代全額を請求できるのでしょうか。それとも、通常の使用により生じた価値減少分を差し引いた金額のみ請求すべきなのでしょうか。
このように「対象物に生じた時間経過をどのように評価するのか」という問題を、経過年数の問題といいます。
以下、物的範囲の問題と経過年数の問題にわけて説明します。
POINT:粗暴な使い方をされた場合は借主負担のケースもある
まず、物的範囲の問題について。粗暴な使い方をした結果、発生した損耗の修復費用は借主が負担することになりますが、その負担は必要な限度を超えてはなりません。
この点について、前述のガイドラインは、クロスについて「平方メートル単位が望ましいが、借主が毀損させた箇所を含む一面分までは張り替え費用を借主負担させることができる」としています。
経過年数の問題については、ひどい使い方をした結果発生した損耗の修復費用は借主の負担となりますが、時間の経過により価値が減少するものは、経過年数が長いほど借主の負担は少なくなるのが原則です(経過年数が考慮されないものもあります)。
ガイドラインは、クロスについて、6年で残存価値が10%(6年目以降は一律10%)となるような直線(または曲線)により残存価値を判断することとしています。
請求できる・できないの判断はどうする?
![]()
借主が4年間の契約を終了してマンションを退去しました。部屋のクロスには、荷物を運び入れた際につけた大きなキズが残っていました。部屋全体のクロスの張り替え費用を請求したところ、「一部負担は止むを得ないと考えていたが、全体の張り替え費用を支払う気はない」との返答でした。費用全額は請求できないものなのでしょうか。
借主への説明責任を定めた東京都条例
平成16年10月1日から、借主への説明責任を定めた東京都条例「東京都で賃貸住宅紛争防止条例(東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)」が施行されました。
この条例は、東京都内に存在する不動産業者に対して、入居中の修理や原状回復の費用負担に関して、まず法律の一般原則を説明し、次に実際の契約での費用負担特約がどうなっているのかを、独立した書面で借主に説明する義務を課したものです。
この条例は不動産業者が対象であり、不動産業者以外の貸主は規制の対象ではありません。
また、主に居住を目的とする建物が対象で、倉庫や店舗の賃貸借には適用されません。
東京都の物件を扱うすべての仲介業者が、条例で定められる説明をきちんと行えば、原状回復に関する紛争は大幅に減少すると考えられます。
そして、この東京都条例により、原状回復に関する紛争が減少すれば、同条例は、他の地域の仲介業者にも多大な影響を与えるでしょう。
トラブル解決の指針となる公的ガイドライン
![]()
敷金精算と原状回復をめぐる苦情、トラブルの増加に対応するため、旧建設省は平成11年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発行しました(平成16年2月に国土交通省住宅局が改訂)。
このガイドラインには、さまざまな事例について、貸主と借主のどちらが費用を負担すべきかという基準が、明確にされています。
強制力はありませんが、裁判所が概ねガイドラインに沿った内容で判断する場合が増えており、事実上法律と同様の効果を持ち始めています。よって、当サイトでもそれを基準として検討したいと思います。
賃貸借契約における「通常の使用による損耗」については、あくまでも貸主が負担すべきであり、借主は粗暴な使い方により発生した損耗だけを費用負担すればよいことが、ガイドラインにおいても確認されています。
ガイドラインが提示する「通常使用による損耗と通常使用を超える損耗の区別」、及び「借主が原状回復義務を負う場合の修繕の範囲」については、リンク先の損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表と借主の原状回復義務等負担一覧表を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
行政のガイドラインについて知りたい
![]()
原状回復をめぐるトラブルについては、行政が定めた「ガイドライン」を基に解決が図られていると聞きました。また東京都では、条例によって原状回復に関する費用負担について説明することが義務付けられていると聞きました。詳しく教えてください。
原状回復特約と消費者契約法
では、原状回復に関して契約書に特約がある場合、「消費者契約法」では、どのように判断されるのでしょうか。
消費者契約法は、事業者が不当な方法で契約を結ばせたときに、消費者がその契約、不利益になる契約条項の全部(または一部)を無効にすることを認めた法律です(平成13年4月1日施行)。
消費者契約法が適用される賃貸借契約においては、「通常の使用による損耗」を借主が負担するという特約が有効かが争点となった場合、借主に有利な判断が下される可能性が高くなります。
判例を見ても、大阪高裁はこうした特約が「借主の利益を一方的に害するもの」であり、消費者契約法10条に反するため無効であると判断しています(平成16年12月17日判決)
今後は、この判例のように、消費者契約法を根拠に原状回復特約について検討するケースが増えていくことが予想されます。
ただし、具体的な事情はそれぞれ異なるため、常に特約の効力が無効と判断されるかどうかは一概にはいえません。
借主負担は一切認められないか
ここで貸主側からは「〝通常使用による損耗〟の修繕費用を借主に請求することは絶対に認められないのか」という疑問が出るかもしれません。
実はこの点については、※「強行法規(民法90条参照)」に反しなければ、借主が負担すべきという特約が有効になる場合があります。
※ 強行法規……当事者が合意する・しないにかかわらず、守らなければならない規定のこと。
では、どんなときに借主に負担してもらうことが可能になるのでしょうか。
判例の流れは、
① 特約の必要性があり、暴利的でないという客観的で合理的な理由が存在すること
② 通常の原状回復義務を超えた修繕義務を負うことを借主が特約から認識していること
③ 借主が特約による義務を負担すると意思表示をしている
以上の3つの要件が必要であるとしています(伏見簡裁/平成7年7月18日判決)。
これらを一つずつ具体的に見ていくと、以下のようなことが必要になります。
①では、物件が周辺の家賃相場と比べて明らかに安いため修繕費用くらいは借主に負担してもらう必要があること、また、修繕の範囲や費用が妥当で、特に暴利的ではないこと。
②では、「通常使用による損耗」の修繕費用は借主が負担する必要はないという原則があるが、この契約では例外的に負担することになっている、と契約者本人に理解させること。
③では、将来借主の負担を予想させる修繕費用がどの程度になるのか、工事項目、工事内容、工事項目ごとの概算費用を具体的に明示しておくこと。
もし、このうちのどれかが欠ければ、貸主は借主に「通常使用による損耗」の修繕費を請求できなくなります。
もっとも特約の有効性については、居住用物件と営業用物件で、多少判断が異なります。
居住用物件では、述べてきたように厳しい要件を満たす場合にのみ有効で、簡単には認められないのが現状です。
POINT:営業用物件は特約の効力が高い
一方、営業用物件については、居住用物件に比べて特約の効力が有効と判断されるケースが多い傾向にあります(東京地裁/平成17年5月18日判決、東京地裁/平成17年4月27日判決、東京高裁/平成12年12月27日判決)。
特約は有効か?
では、質問のように「借主は、故意過失を問わず、建物の毀損・滅失・汚損その他の損害につき損害賠償をしなければならない」という特約がある場合はどうでしょう。
この場合、貸主は「通常生活による損耗」についての修繕費用負担を借主に請求できるのでしょうか。
この点について、最近の裁判例では質問のような特約がある場合でも「ここでいう損害には、賃貸物の通常の使用により生じる損耗は含まれない」と、特約の効力を限定的に解釈したり(名古屋地裁/平成2年10月19日判決)、特約自体の有効性を否定したりしています。つまり、「通常生活による損耗」は、やはり貸主が負担すべきとする傾向にあるのです。
ですから特約があっても、原則として「通常生活による損耗」について借主側が修繕する必要はないと考えられます。したがって、借主が普通に生活をしている限りクロスやカーペットを新品にしての返還請求をすることはできません。
原状回復義務の内容
![]()
借主には、賃貸借契約終了の際、その物件をもとの状態に戻してから、貸主に返還すべき義務があります。これは「原状回復義務」というものです。
しかし、貸主は建物を貸すことで家賃収入を得ていますので、明け渡しのときにすべて新品にして返還されるのであれば、貸主はそれだけ不当に利益を得ることになります。
そこで原則として、「通常使用による損耗」については、修繕費用を請求する権利はないのですが、故意・過失による損耗の回復に限っては請求が可能です。